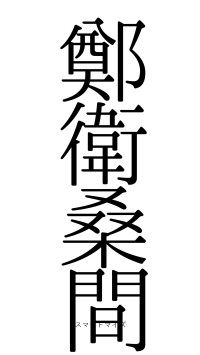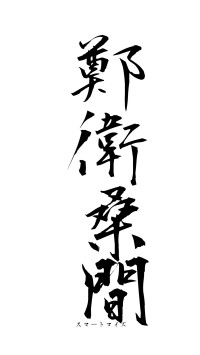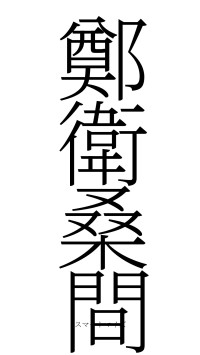鄭衛桑間(ていえいそうかん)の意味と読み方 - 四字熟語辞典
四字熟語辞典「鄭衛桑間」の意味を解説します。
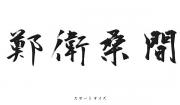
鄭衛桑間
- 読み方
- ていえいそうかん
- 意味
- 国を滅亡に導くほどの下品で淫靡な音楽のこと。
- タグ
- 「て」から始まる四字熟語




「鄭衛桑間」の意味・使い方・例文|軽薄で淫靡な音楽を指す四字熟語
「鄭衛桑間(ていえいそうかん)」とは、世俗的で享楽的な音楽や風俗を表す四字熟語です。元は中国の古典に由来し、道徳的に好ましくないとされた音楽や文化を批判的に指す言葉です。

「鄭衛桑間」の詳しい意味
- 意味: 享楽的で節度のない音楽や文化を指す。
- 語源: 中国の春秋戦国時代、鄭や衛の国で流行した音楽が、当時の儒者から堕落したものとみなされたことに由来する。
- 類義語: 「靡靡の音(びびのおん)」「軽佻浮薄(けいちょうふはく)」
- 対義語: 「雅楽(ががく)」「正統音楽」
「鄭衛桑間」を使った例文と使い方
-
流行音楽を批判的に表現する
例文: 「最近の音楽は鄭衛桑間のようだと嘆く人もいるが、それも時代の流れである。」
使う場面: 現代の音楽を伝統的な価値観から批判するとき。
ポイント: あまりに厳格に使うと古臭い印象を与えることも。 -
娯楽文化の変化について語る
例文: 「インターネット時代になり、鄭衛桑間のような文化がますます広がっている。」
使う場面: 文化や娯楽の変化を指摘するとき。
ポイント: 「風紀の乱れ」や「享楽的な傾向」などと合わせて使うと分かりやすい。 -
歴史や哲学的な文脈で使う
例文: 「儒教の観点では、鄭衛桑間の音楽は人々の精神を乱すものとされていた。」
使う場面: 歴史や哲学の話題で伝統的な価値観を説明するとき。
ポイント: 「礼楽」「道徳」といった概念と組み合わせると深みが増す。
「鄭衛桑間」の注意点
この言葉は古典的な表現であり、現代ではあまり日常的に使われません。批判的な意味合いを持つため、適切な文脈で用いることが重要です。
「鄭衛桑間」の関連キーワード
享楽、風紀、伝統、音楽史、堕落、文化批評